魯山人の料理修行
2023年01月30日
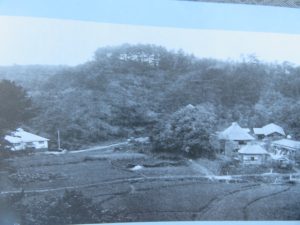 鎌倉・星岡窯(昭和2年の開設当時)
鎌倉・星岡窯(昭和2年の開設当時)
「料理も芸術なり」
とは、魯山人が三十代の初め内貴清兵衛から教え込まれて以来、自らも信条とした言葉であった。料理も芸術とは、要するに料理の‶味〟によって、人を高い感動に導くということに他ならない。
わたしは初め、料理についてかくべつの修行もしたことのない魯山人がなぜ、東都の第一流の料亭を睥睨し、自ら料理長として君臨できたのかを容易に理解できなかった。
天ぷらや刺身はどうであったか。
魯山人は要するに、幼少の頃養父母の飯炊きや総菜作りをし、内貴清兵衛の別荘で料理を作り、金沢の料亭「山の尾」で料理について教わったといっても、本職としての修行はしていないではないか。
昭和六十一年春、わたしはそれまで電話や文通だけしていた、松浦沖太を箱根の三井物産湖山荘に訪ね、初めて彼が魯山人の星岡茶寮に在った数年間についてきいた。
松浦は、年わずか二十二で二十数人もいた料理人の中から、一躍抜擢されて料理主任にされた人である。わたしは他の料理人から、魯山人らしい独断専行だったという批評をきいて、いかにもそうだと思っていた。
松浦をいきなり料理主任に抜擢したとき、星岡茶寮寮内には当然、批判や非難がくすぶった。そのとき魯山人は、明言したという。
「松浦が一番味がわかるから、主任にしただけの話だ。年が若すぎるなどとかげで文句をいっている奴がいるというが、笑いばなしだよ、料理人は味がわかることが、第一なんだ。上手に刺身を作ったり天ぷらを揚げたりすることなら長年やって巧くなるに決ってる。味だけはもって生れたもんだ。年期をつめばわかるようになるというもんじゃないし、教えて教えられるもんでもない。鯛のうしおはこう作ると教えれば誰でもまねはできるがその通りの味はできるもんじゃない。星岡の主任は味さえほんとにわかるもんなら、なに、女だって子供だって、俺はえらぶんだ」
若年のころわたしは、やきもの作りで魯山人が自分では挽けず(仮に挽いたとしても巧くなく)職人に挽かせていたことを以て、世を詐る山師の所業として憎み、蔑んだ。
その後歳月と共に、轆轤を挽かぬ魯山人からはなれて独立してみると、凡作しか作れぬ秘密を次第に理解するようになった。
すなわち、魯山人はいかなるやきものが芸術作品たり得るか、雅致に富む作品たりうるかを、この上もないほどに的確に知っていたのである。料理でいえば、いい味とはどういうものか、どうすれば作り出せるかを知っていた、ということとまさしく同じことであった。
絵にしても篆刻にしても、およそ彼のいう芸術についての認識に関するかぎり、魯山人はおそろしいまで的確に最も大切なものを見すえて、誤またなかったのである。
彼は‶味〟を、星岡茶寮に於て集中的に、或いは最も純粋に表現しようとした。時間的相対的で如何とも客体化することのできない味というものに、魯山人は全力を傾注したのである。
日本的伝統を重んずる彼は、料理には必ず適切な器が必要であり、さらに環境が重要であると考える。ために器を自ら作るに至り、星岡茶寮という物理的にも大がかりな構造を必要としたのである。
中村竹四郎という辛抱強く理解のある協力者を得て、十年あまり彼の理想に近い味の演出はつづいた。今にして思えば、ほとんど奇蹟に近いといえよう。
星岡茶寮は、所詮料亭であり、商売であり、多くの協力者を必要とする。魯山人が純粋に‶味〟だけを固執して行くことは、元来至難な事業である。
星岡茶寮は、むしろ中村の忍耐の故に長く続きすぎた位であった。敗戦を経て生活は次第に衰微して行ったように見える。
そうではない。彼は純粋に自分の芸術制作活動に帰ったのである。星岡茶寮は昭和十一年に退いて、彼の芸術制作活動は本来の軌道に戻ったのだ。
晩年だれも訪ねて来ず、雨漏りのする山荘で、なお筆を揮い、土をこねつつあったとき、魯山人はついにまことの芸術家のかがやかしい生活を送っていたのである。彼はすでに、貧困の恐怖からも脱していた。文部技官小山富士夫が重要無形文化財の指定受諾をわざわざ二度までも懇請に来たのを峻拒したとき、あれほど近づきたいと念願していた世俗的成功をも、弊履の如く投げすてていたのである。
文~白崎秀雄(作家)
 芸術新潮 一九八七年九月号より
芸術新潮 一九八七年九月号より
 今朝の
今朝の
 海
海
 と
と
 自給自足
自給自足
 生活を
生活を
 めざして…
めざして…

そば会席 小笠原
北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100
FAX:電話番号と同じ
E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp
営業時間:10:30~21:30
定休日:月曜日
