中央バス開祖 杉江仙次郎
2021年12月20日
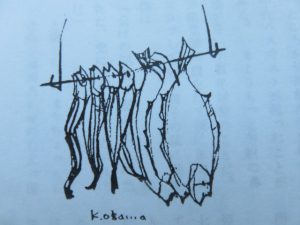
間もなく新しい年が訪れようしている昭和二十八年十二月気息えんえんの仙次郎は年来の友人、松川嘉太郎を己の病室に招いた。昏睡状態からいっとき醒めた仙次郎は自分に万一のときは中央バスのことを…と喘ぎながら言葉にした。友の顔をいちべつしてもう死相とみてとった松川は応諾した。
杉江仙次郎が後事を松川に託したことは結果的にバス会社にとって大吉だった。昭和43年の現在、北海道中央バス株式会社は積雪寒冷地の北海道に会って最も充実した道内バス業界の雄となったのだから。
小樽にバスらしいバスが初めてお目見えしたのは大正九年(一九二〇年)のこと、当時の資本金で五万円「小樽市街自動車株式会社」といった。手宮駅前から若松町まで第一大通りをトコトコ走って片道十銭なり。現在は一区間十五円。通称赤バス(実際は茶褐色のボデイ)時代である。
ところが翌十年、同じ社名で青バスが走り始めたのである。市外を走るバスは銀色。赤、青で激しいせり合いを展開したことはいうまでもない。
いまは懐かしい名称「乗合バス」十銭玉をだして皆で乗り合うから簡潔にノリアイバス。そんな企業に仙次郎が乗合ったのは昭和七、八年ころ。日支間に風雲急を告げ、世の中が次第にカーキー色と軍靴の音で覆われ始めていたときである。
仙次郎は七十六年の生涯のスタートを愛知県常滑市できっている。本誌昨年十二月号に綴った稲葉林之助の従兄弟。だから林之助が小樽で一店を構えたときに、早速呼ばれて船具、鉄鋼業の店員として骨身惜しまず働いた。
林之助が一戸を構えたのが明治二十六年、仙次郎が漸く独立したのは同四十二年、この間十余年の歳月を重ねている。日露の大戦でやっと世界の列強に仲間入りしたばかりの日本帝国を背景に、海外に目を開き始めた小樽という港町が舞台とあってみれば、人よりほんの僅かでも頭の回転の早い人間なら商いの道になにかアイデアを生かした筈。
ところが仙次郎は主家稲葉商店で身につけた船具、鉄鋼業の営業をさらりと忘れて始めたのは、主家と同じ商売で対立しては申し訳ないという律儀精神からである。
今日の車の全盛時代を迎えている。石油販売業がウケに入っていることも現実、だがよもや明治末期に石油店を営むことが彼の子孫に美田を残すとまで先見の明があったとは思えない。
しかしこの方針は間違っていなかった。松山嘉太郎社長が杉江を「ともかく知謀の人だった」と述懐している。仙次郎は岩見重太郎が好きで旅先の宿でも専ら岩見重太郎の講談や文庫を買わせたというが強者に憧れていたのかも知れぬ。
戦前の小樽市内に於ける石油卸商といえば国油商会、亀岡商会、河辺商店、酒谷商店、板谷商船、三忠商店、越崎商店、小滝商店、稲葉商店、荒田商会などがあり、そして三菱石油を扱う杉江商店が並んでいた
そして戦後……。
新しい店が続々と石油スタンドを開設しているが前記の店のうち同じ石油卸商が何軒あるかは読者の方が詳しい筈。
杉江商店が石油を売り始め、その杉江仙次郎がガソリンを喰うバス企業をやらざるを得なくなっためぐりあわせは面白い。
「人は死ぬまで働かなければならぬ」「他人を頼ってはいけない」「人を保証するな」「腹をたてたら負けだ」
俗にウチ弁慶という家庭に厳しく外にやさしい性格の仙次郎が常日頃、家人に繰返した数々の言葉である。どれ一つを挙げても商人として当然ふむべき道理を彼は己の体験を通じて覚り、そのことを周囲の人に徹底させようと努めた。
だが必ずしも外柔内剛とばかりいえぬ一面も持ちあわせていた。民政党の前、昭和会を一生懸命育てあげた政治力もあり、選挙といえば応援弁士を買ってでた。
エリートの親睦団体「ロータリークラブ」が政治色は禁物と聞いて自分の方から入会を断った骨ある商人である。
さてバス会社の話にもう一度戻る。昭和十八年に札幌、小樽のバス会社が戦時統合して中央バスがは発足して杉江仙次郎が初代社長になった。バスの走りにくい狭い坂道の町小樽に本社を置くことが仙次郎の念願でこれを実現した。ただ儲けることだけに猛進していたら、彼は稲葉商店から独立したときに、覚えた船具商を開店しただろうし、バス経営は道巾の広い、平坦で四方八方に脈絡のつけ易い札幌を基点とした方が遥かに得策とした筈である。
功利主義的な当節の感覚でゆけば仙次郎のとった方針は極めて浪曲的であり、涙腺刺戟にはもってこいの修身講話で。だが後世人がどう批評しようがそんなことは問題ではない。仙次郎が己の体に感じ、肝に銘じた小樽での人生経験が最後まで港おたるに執着させた。
大混乱の終戦が訪れた。木炭をたいて走っていた車が再びガソリンを燃料として快走する時代となったものの、バス企業の内容は決して楽なものではなかった。会議所議員、会頭そして市会議員を務めていた仙次郎の盟友は砂糖を商っていい意味での甘い汁を十二分に貯えた松川嘉太郎その人だった。
松川も大正十五年から市会議員であり、昭和会の闘士として活躍し、戦後も商工会議所会頭の重鎮にあった。仙次郎が兄弟づきあいの松川をバス会社経営の相談相手にしたのは、己の病が不治のものであり、命数あと幾ばくもなしと自覚したときだったかも知れない。
仙次郎には娘千代子の夫猛がいる。娘婿に一切を委せて然るべきであるのが常識だ。それが松川に後事を託した。何故だったろう。現中央バス専務の猛は大正十四年に小樽高商(現樽商大)を卒業したインテリであり杉江商店は勿論、三馬弘進ゴム工業の経営、全国石油販売協組連の理事としての仕事をこなし市会議員や港湾審議会委員の養殖も経験している有為な人材だ。
ところが仙次郎の生前時代に中央バスでストが起ったことがある。いまよりももっと労組の鼻息が荒い十数年前のことだ。労組交渉に腹をたて頭にきてカッカッしている養子の猛に仙次郎は
「公の問題で怒ることは禁物だ、先に腹を立てた方が負けだ」
と諭した。つまりちょっとした性格が清濁あわせのむ太っ腹なものにせいちょうするまで、いっときワン・クッションを置く意味で盟友松川を選んだとも考えられる。この頃の中央バスは三千万円の資本金でありながら借りいれ金が実に二億七千万円だった。
しかも仙次郎が息を引取った翌年末(二十九年)までに一億七千万円は返済することになっていたのである。当時もし猛一人でこの難関を突破しようとしたらかなりの苦戦は免れなかったかも知れず、松川嘉太郎のカオが大いにものを言ったことは今日の小樽経済人なら誰もが知悆している事実、血脈の情に溺れぬ仙次郎の目は息を引取る寸前まで狂っていなかった。
安物買いのゼニ失ないを極度に嫌った仙次郎だが、ゼニはださぬまでも何人かの社長らとともに名前だけ貸して成功させ得なかった企業が一つ戦後にある。
昭和二十四年の年末から創業した地元紙「みなと新聞」だ。主幹刀根武雄は仙次郎の姪の婿にペンをもたせては道内有数の逸材だったが、ソロバンの方はいけなかった。この地元紙は僅か二年余で消えた。刀根も私財を全部投じた末に胸部疾患が因で不帰の人となった。本当の商人というものは決して新聞などの文化事業に手をだすものではない…小樽に本格派地元紙が育たぬ遠因が「人の保証をしてはいけない」と固く戒めた仙次郎の処世訓を直接間接耳にした小樽商人の間にたちこめているからかも知れぬが。
眉は太短く、眼鏡の奥によく光眼がひらき、でんとあぐらをかいた意志強げな鼻の下に気むずかしいへの字に結んだ口がある。
筆者が潰れた「みなと新聞」のトロッコ記者時代、一度だけ刀根主幹に従って杉江社長の顔に接したときの印象である。だが杉江社長はごく静かな声で「なんでも仕事というものは苦しいものだ。苦しさがあってこそ酬われて得られるものは大切だ。君はまだ若いんだからうんと働くことだ。頼れるものは誰でもない、自分一人だよ」
記憶は定かではないがこんな風なことを聞いたと憶えている。文字通り、腕一本、脛一本で明治末期から大正、昭和と生きぬき戦後のバス全盛という今日にふさわしい企業の礎石を築きあげたその足跡は、やはり小樽経済史のなかで大きいといわねばならぬ。
現社長松川嘉太郎氏が「俺の目の黒いうちは中央バス本社は絶対小樽から動かさぬ」と断言したという現今の伝説(?)がある。
松川社長の小樽固執の源は盟友仙次郎が戦時中統合したバス会社の本社や石油販売統制会社の本拠を断然小樽だと決めて実現させた、ある意味での郷土愛を彼もまた見事に頑なまでに守り通しているのだといってもよかろう。
~続・小樽豪商列伝(7)
月刊 おたる
昭和42年8月号~44年6月号連載
里舘 昇
『2021年12月19日現在の小樽市内のバス料金は
240円です。』

そば会席 小笠原
北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100
FAX:電話番号と同じ
E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp
営業時間:10:30~21:30
定休日:月曜日
